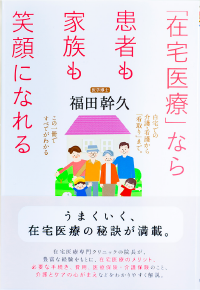2017年度実習生
H29.1.25 初期研修医1年目 金子 峻介
 私が研修させて頂きました日は積雪のため、患者様の御宅やグループホーム様のところへ辿り着くことがとても大変に感じられました。しかし、こうした時にも診察が必要となる患者様方が確かにおられるのだということを同時に痛感いたしました。
私が研修させて頂きました日は積雪のため、患者様の御宅やグループホーム様のところへ辿り着くことがとても大変に感じられました。しかし、こうした時にも診察が必要となる患者様方が確かにおられるのだということを同時に痛感いたしました。
在宅医療という選択肢を採ることは、本来疾患が無ければ自宅で過ごすという極当たり前の状態に近づくという社会的に大きな意味を持つことだと存じます。近年は「患者中心」の医療を提供することが叫ばれ、一人ひとりのニーズに応じた適切な医療サービスの供給という考えが主流となっております。こうした中で在宅医療の占める位置は今後ますます重要なものになると考えております。
今回その現場を目の当たりにし、その実際を記憶できたことで普段病院内でいるだけでは思いつかないような、患者様の日常に触れることが出来ました。この経験は必ずやこれからの自身の診療に好影響を与えてくれるものと考えております。
こうした機会を与えてくださったひだまりクリニックの先生方、スタッフの皆様方への感謝を述べてこの文章を締めくくらせていただきたいと存じます。本当にありがとうございました。
H29.5.22 鳥大医学部医学科6年生 松田 梨沙
 “「在宅医療」なら患者も家族も笑顔になれる”と、院長先生が本のタイトルにつけているとおり、この5日間はたくさんの人の笑顔を見ることができて、私も自然と笑顔でいられることが多かったように思いました。5日間いるだけでも、いろいろなお家に訪問して、いろいろな人とお会いできて、そこに触れ合えるのは訪問診療の醍醐味であると感じました。
“「在宅医療」なら患者も家族も笑顔になれる”と、院長先生が本のタイトルにつけているとおり、この5日間はたくさんの人の笑顔を見ることができて、私も自然と笑顔でいられることが多かったように思いました。5日間いるだけでも、いろいろなお家に訪問して、いろいろな人とお会いできて、そこに触れ合えるのは訪問診療の醍醐味であると感じました。
さまざまな患者、家族さんがいて、すべての人がそうと言うわけではありませんが、終末期にある患者さん、不自由なことや思い通りにならないことがいくつもある状態でも、患者さん、一緒におられる家族の方は、とても穏やかな表情であることが多かったように思いました。自分ではまだ実感が持てませんが、多くの患者さんにとって、住み慣れた自宅というのは、安心の得られる場となっていることが分かりました。
訪問診療に同行させていただいて、ケアマネさんや、患者さんが通っている施設の看護師さんといったさまざまな職種の方にお会いすることが多かったように思いました。大学病院での実習でも、多職種によるカンファレンスを見ることはありますが、患者さんも家族の方も、ホームグラウンドでおこなわれるカンファレンスの方が、リラックスできて意見も言いやすいし、先生方も患者さんの実際に生活する場を確認できて、少なからず病院で診るよりも素の患者さん、家族の方を見ることができて、より有意義なものであるように思いました。
大学では多くの疾患、それに対する治療法を学んできました。しかし、こういった現場では根本的な治療法がないことの方が多く、医師の無力さというものを痛感しました。ただ、患者さんのところに行き、患者さん、家族の方、医療関係者の方と話し合って、みんなが一番幸せになれるように最善をつくす、また、患者さんや家族の方に呼ばれたら訪問させていただく、困っていることを一つでもよくする。そうすることで信頼を得て、患者さんのそばに寄り添うことができるのが在宅医療のよいところであり、必要なことだと思いました。
ひだまりクリニックのみなさん、親切にしていただいて、たくさんのことを教えていただいて、本当にお世話になり、ありがとうございました。また、今回訪問させていただいたみなさんに、学生の私を快く迎え入れてくださったことに、感謝の気持ちでいっぱいです。
H29.5.29 鳥大医学部医学科6年生 吉岡 俊樹
 この度、大学のポリクリ2の一環としてひだまりクリニックで一週間実習させていただきました。今までの実習は大学病院内がほとんどであり恥ずかしながら在宅医療について全く理解していませんでしたが、今回の実習を通して在宅医療についての理解を深めることができました。
この度、大学のポリクリ2の一環としてひだまりクリニックで一週間実習させていただきました。今までの実習は大学病院内がほとんどであり恥ずかしながら在宅医療について全く理解していませんでしたが、今回の実習を通して在宅医療についての理解を深めることができました。
実習を通して感じた在宅医療のメリットとして「患者さんの満足度が高い」ということがあります。医療従事者のペースで1日が進む病院と比べて、患者さん自身やご家族のペースで1日を過ごせる自宅は患者さんの満足度は高いように感じました。病院の回診では患者さんやご家族は言いたいことがあってもなかなか言い出せない雰囲気にあることが多いですが、在宅では患者さんとそのご家族、医師、看護師の距離が近くリラックスした雰囲気で会話がされているのが印象的でした。また実際に入院から在宅に移行された患者さんが家に帰った途端、活気を取り戻し検査数値も改善することがある、といったケースも伺いました。
また持続可能な医療制度という視点からも在宅医療は大きな役割を果たすことが期待されています。居宅での在宅医療と介護を受けた場合、入院医療と比較して社会保障費は1/3程度とも言われています。高齢者を病院で看取る医療はベッド数・財政的に限界があり、持続可能な社会の為にも今後とも在宅医療が推進されていくことが考えられます。
私が感じた今後の在宅医療の課題として、「在宅医療に従事する医師の不足」があります。私が経験した一週間の実習では忙しい日には一件あたり20分の移動時間、診察時間10分といったこともありました。訪問診療は病院と違いどうしても移動時間がかかってしまうので多くの患者さんを診察する必要がある場合、医師・看護師ともに気が競ってしまい患者さん一人ひとりに向けられる余裕がなくなってしまうのではないかと思いました。また現在ひだまりクリニックは常勤医師2名、24時間体制で運営されており夜間の往診もあるため常勤の先生方の負担は少なくありません。他の分野にも共通することですが持続可能で効率のよい在宅医療を届けるために、今後はチームでの診療所の運営が重要になると感じました。
「在宅医療は地域という大きな病院の中で患者さんの部屋(家)に伺い診察を行います。」と表現すると医学生にはイメージがつきやすいかもしれません。私は今回の実習でそのようなイメージを持ちました。大学のカリキュラムでは医学生の実習はほとんどが大学病院・市中病院で行われ、そこで行われる診断・治療についての理解は深められます。しかし在宅医療の実習時間はほとんどないため、在宅医療を体験し理解する機会は少ないのではないでしょうか。例え総合病院に勤務しようとも医療を一つの施設で完結させるのではなく、地域全体で包括的な医療を提供するという意識を持つことが大切だと思います。今後はより多くの医学生が在宅医療を体験してそれに気づく機会が増えることを期待しています。今回の実習を受け入れてくださったひだまりクリニックのスタッフの皆様、患者さん、ご家族の皆様、本当にありがとうございました。
H29.6.19 鳥大医学部医学科6年生 山地 亮輔
近年では、60%以上の国民が終末期の療養場所として自宅を希望するなど、在宅医療に対する国民のニーズが高まっています。また、日本の人口動態からますますこの先、死亡数が増加し、ベッド数が不足してゆくため、国を挙げて在宅医療が推進されていくことと思います。
しかし、在宅医療に対する理解はまだまだ進んでいないように感じます。かくいう私もその中の一人で、これまでの実習は大学病院や市中病院を中心としたものであり、あまり在宅医療には馴染みがなく、どこか遠いことのように感じておりました。今回、1週間という短い期間ではありましたが、在宅医療の実際を見学させていただけたことは、大変刺激的で意義のあるものになったと感じております。
個人的には、在宅医療といえば慢性期の患者さんや看取りのイメージが強く、在宅医療でどこまで可能なのかというところがありました。患者さんやご家族の皆様につきましても、病院を離れて自宅で過ごすことに対して不安を感じることと思います。しかし、実際に在宅医療の様子を見学させていただいたところ、多くの患者さんがのびのびと生活されており、しばしば笑顔を見せてくださることが印象的でした。ひだまりクリニックでは、在宅医療を専門とし、医療・福祉の各サービスと密に連携をとることで、24時間体制で在宅医療を提供することを実現しておられます。また、実際に患者さんのご自宅まで足を運び、その様子を知ることで、細かいところにまで目の行き届いた、患者さんとそのご家族ごとに合わせた医療が提供されていました。さらに、私が想像していたよりも幅広い患者さんを在宅で診ておられ、それは診療所で患者さんを診るのと遜色ないものでした。入院や通院は非日常的なイベントであり、患者さんは医療機関のペースに合わせなければならないことも多くストレスを感じることと思います。それに対して在宅医療は、患者さんとご家族の日常生活をベースとし、それを支持していくものです。その満足度の高さは、在宅医療を開始した患者さんの検査値が退院前より改善したという話からもうかがうことができますし、何より患者さんのリラックスされた表情が物語っていると思います。これは在宅医療の大きな魅力であると感じました。また、これを実現するのが患者さんを中心とした多職種連携であり、その現場を間近で見学させていただけたことは大変勉強になりました。
最後になりましたが、お忙しい中で、実習の機会を与えてくださったひだまりクリニックのスタッフの皆様、そして学生実習を快く受け入れてくださった患者・家族の皆様につきましては、まことにありがとうございました。今回得た学びを胸に、患者さんの心に寄り添える医師を目指して精進していく所存です。
H29.6.27 鳥大医学部医学科6年生 吉田 つばさ
 「在宅専門のクリニックってどういうことだろう?」
「在宅専門のクリニックってどういうことだろう?」
臨床実習?でひだまりクリニックに行くことを知ったとき、こんな疑問が浮かびました。今までも実習やサークル活動で訪問診療を見学することは何度もありましたが、どの医療機関でも外来診療を行っており「訪問診療しかしていない」というところは初めてだったためです。さらに1週間も訪問診療に同行することも初めてで、疑問と発見に明け暮れた5日間でした。 この1週間で学んだことを2つ挙げようと思います。ひとつは『設備や環境面では病院と大差ない』ということです。特に驚いたのは検査が拡充していたことでした。採血や尿検査だけでなく、心電図、エコー、X線、培養まで在宅医療で行えます。できないのはCTとMRIくらいのものです。また、医師が24時間365日急変に対応するため、入院から在宅に移行するハードルは想像していたよりももっと低いのかもしれないと感じました。
もうひとつは『患者の懐に入ることの重要性』です。入院治療では患者が病院という医者のテリトリーにいますが、訪問診療では自宅という患者のフィールドに医師が出向きます。病院より自宅の方が患者のストレスが少なくなることも大切ですが、写真、表彰状、本、仏壇、ペットなど、患者の生き様や暮らしぶりを医療者が実際に体感できることも訪問診療のメリットのひとつだと思いました。実際の患者さんの中に、飾ってある表彰状を話題にすると涙を流す方がいらっしゃいました。その表彰状がその方にとってどれだけ重要なのか、入院治療をしていたら気付けなかったかもしれません。相手の懐にこちらから飛び込む大切さを改めて感じました。
高齢化、多死社会になり、人生の終え方の選択肢も増えてきました。延命治療を望む人と望まない人、病院で亡くなる人、自宅で亡くなる人、施設で亡くなる人、家族に見守られて亡くなる人、あえて独りで逝くことを望む人……いろんな終え方があっていいと私は思います。しかし、その中でも『自宅で亡くなること』はまだ容易に選択できる状況ではありません。患者自身の最も望む人生の終え方の選択肢のひとつとして、24時間365日対応できる訪問診療はもっと広まるべきだとこの実習を通して改めて感じました。
1週間という短い期間でしたが、在宅専門のクリニックがどんなものか、どんな思いを持ってどんなことをしているのかを学ぶことができました。特に最初に書いた『在宅専門』という疑問ですが、クリニックの特色として在宅専門にしたとのことでしたが「この忙しさでは外来診療なんてできないだろうな」というのが正直な印象です。いつ急変があっても対応しなければならない大変さはよほどの信念がないとできないことだと思いますが、その分どの患者さん・ご家族もひだまりクリニックの医師や看護師を信頼しているのが初対面の私にも分かり、どの患者さんも幸せ者だと感じました。私は将来何らかの形で在宅医療に関わりたいと考えています。この1週間で感じたことを忘れずに、自分の患者にも幸せ者になってもらえるように頑張りたいと思います。
1週間本当にお世話になりました。ありがとうございました。
H29.7.18 鳥大医学部医学科6年生 細田 利奈
 ひだまりクリニックでは在宅医療とは実際どのようなものか学ぼうという思いを持って実習させていただきました。在宅医療と聞くと介護などが大変であるなど、どちらかというと暗いイメージでした。実際に在宅医療の現場について行くことでそのイメージはなくなったように思います。短い時間しか様子を見ていないですし、大変なことはもちろんあると思われますが、患者さんやご家族の穏やかな雰囲気が印象に残っています。在宅医療だからこそ感じることのできる普段の生活を送っている時のような穏やかさなのではないかと思いました。私は大学病院で実習をしている時などに、もし自分が入院しても家には帰りたいなぁ…と考えることがあります。住み慣れた家に帰りたい、家族と過ごしたいということを在宅医療ではできると思いました。そのためには、在宅医療の体制が整っていることと、様々な職種や家族などの協力がなくてはならないと強く感じました。また、今回の実習では高齢の方の訪問診療がほとんどで、これからより高齢化が進む中、在宅医療は非常に重要になってくると改めて思いました。これから在宅医療が充実していけば良いなと思います。在宅医療が充実していくにはどういうことが大切か、これから私なりに考えていきたいと思っています。
ひだまりクリニックでは在宅医療とは実際どのようなものか学ぼうという思いを持って実習させていただきました。在宅医療と聞くと介護などが大変であるなど、どちらかというと暗いイメージでした。実際に在宅医療の現場について行くことでそのイメージはなくなったように思います。短い時間しか様子を見ていないですし、大変なことはもちろんあると思われますが、患者さんやご家族の穏やかな雰囲気が印象に残っています。在宅医療だからこそ感じることのできる普段の生活を送っている時のような穏やかさなのではないかと思いました。私は大学病院で実習をしている時などに、もし自分が入院しても家には帰りたいなぁ…と考えることがあります。住み慣れた家に帰りたい、家族と過ごしたいということを在宅医療ではできると思いました。そのためには、在宅医療の体制が整っていることと、様々な職種や家族などの協力がなくてはならないと強く感じました。また、今回の実習では高齢の方の訪問診療がほとんどで、これからより高齢化が進む中、在宅医療は非常に重要になってくると改めて思いました。これから在宅医療が充実していけば良いなと思います。在宅医療が充実していくにはどういうことが大切か、これから私なりに考えていきたいと思っています。
今回の実習で、大学病院では見ることのできないものを見ることができました。24時間365日対応する忙しさ、移動時間があること、先生・看護師の方の大学病院とは少し違う雰囲気などを感じ、在宅医療について考え、充実した4日間の実習になりました。今回学んだことを忘れずに過ごしていきたいと思います。ひだまりクリニックの先生方、スタッフの皆様、訪問先の患者さんとご家族の皆様、本当にありがとうございました。
H29.7.24 鳥大医学部医学科 6年生 山本 栞里
 私はこれまで何度か訪問診療に同行させていただいた経験はありましたが、5日間連続訪問診療にどっぷり浸かるという経験は今回が初めてでした。5日間を終えた率直な感想としては、思っていたよりハードで、訪問診療の楽しさだけでなく、介護負担やサービス利用、病院との連携、終末期医療など、患者さんを通して地域の医療を垣間見た日々でした。
私はこれまで何度か訪問診療に同行させていただいた経験はありましたが、5日間連続訪問診療にどっぷり浸かるという経験は今回が初めてでした。5日間を終えた率直な感想としては、思っていたよりハードで、訪問診療の楽しさだけでなく、介護負担やサービス利用、病院との連携、終末期医療など、患者さんを通して地域の医療を垣間見た日々でした。
1日は朝のカンファレンスから始まります。初日は、前日に診察した方とその日に診療予定の方の人数の多さと内容にただただ圧倒されました。しかし、日を追うにつれて内容について行けるようになり、自分が訪問した患者さんの振り返りもでき、訪問していない患者さんのことも少しはイメージできるようになりました。そして、何よりスタッフ全員で情報を共有し、意見を出し合うことの大切さを感じました。
カンファレンスが終わると訪問診療に出発します。米子に住み始めて6年の月日が経つ私ですが、まだまだ知らない道、初めて見る風景が多く、私の家の近くの患者さんや訪問前からお知り合いだった患者さんもいらっしゃって驚きました。伺った患者さんもご家庭もさまざまでしたが、患者さんの状態や介護されているご家族の方のお話からは、介護の大変さがひしひしと伝わってきました。一方、上思議と介護に疲れ切っているという方は見かけられず、積極的に取り組まれ、ご家庭内で良い関係を築かれていることがとても印象に残りました。私が見た場面はほんの一部で、それぞれ大変なこと、辛い時期を乗り越えられて今があると思うのですが、その過程を共に歩んでこられ、これからも歩み続けていくクリニックの方々の存在は大きいなと思いました。
私の実習初日に体調を崩され、いわゆる終末期に入られた患者さんがいらっしゃいました。疼痛緩和に伴う麻薬の調整や呼吸上全に伴う在宅酸素導入などで、私も頻回お宅に伺わせていただきました。私は、今まで実習や私生活においても看取りに立ち会ったことがなく、最期が近づいている患者さんの身の置きどころの無さ、その姿を近くでずっと見守り続けている家族の方に、かける言葉が見つかりませんでした。そのような状況の中での医師、看護師の話す内容、接し方、タイミングなど、死を前にして避けては通れない、大切なやりとりがあることを間近に見て、学ぶことができました。また、悲しみといった感情が込み上げてくることもありましたが、ご自宅で患者さんに付き添われる家族さんの光景は、ぬくもりと神聖さを感じ、1つの幸せのカタチを目の当たりにしたように思っています。
最後になりますが、福田先生、前田先生をはじめとするひだまりクリニックの皆様、学生の訪問を快く受け入れてくださった患者様とご家族様に、心より感謝申し上げます。
H29.10.11 鳥大医学部医学科4年生 伊原 奈緒
「ひだまりクリニックで実習させていただいて」
 私はこの度、地域医療体験実習という授業を通じ、ひだまりクリニックさんのもとで実習をさせていただきました。2年生の時にケアマネージャーさんとともに在宅の方々のもとを訪れたことはあったのですが、実際医師がどのような医療を提供し、患者さんたちと関わっているのかという点において予備知識もあまり無く、今回の実習を楽しみにしていました。
私はこの度、地域医療体験実習という授業を通じ、ひだまりクリニックさんのもとで実習をさせていただきました。2年生の時にケアマネージャーさんとともに在宅の方々のもとを訪れたことはあったのですが、実際医師がどのような医療を提供し、患者さんたちと関わっているのかという点において予備知識もあまり無く、今回の実習を楽しみにしていました。
午前と午後の両方で各家庭や施設を訪問し、一般的な病院とは異なり、患者さんが主訴→診察→検査→治療という外来の流れではなく、食事や栄養・排泄・皮膚の掻痒や褥瘡・巻き爪などという患者さんにとっての生活の質(QOL)の向上を考えた包括的医療の形体をとっているということがわかりました。医師側の立場を考えると、24時間365日いつ呼び出しの電話がかかってくるかわからず、現在300人をこえる患者さんを訪問しているとのことで医師にとってとても負担は大きいのではないかと思いました。
また、患者さんやその家族、その家庭に入っていくので様々な事情や状況を理解し、ケースバイケースで医師として立場をわけた意見を言うことも大切です。しかし、医師も人間ですし、自然と患者さんやその家族に感情が入ってしまうこともありますが、患者さんとの信頼関係を築くためにそれは必要なことであり、患者中心の医療である、大切なのは医師が自分の理想の在宅医療の確固たる像を持つことであるというお話に非常に感銘を受けました。
高齢者の患者さんの中には「長年暮らしてきた家で死を迎えたい」という考えと「病院等でしっかりと何があっても対応してくれる医療を受けたい」という2つの考えが混在している方も多いと思われます。今まで、この訪問診療や在宅医療というものが確立されていなかった時では、この2つの考えは相反するもののように思われてきたと思いますし、事実私も今日の実習で目の当たりにするまで相反するものだと思っていました。しかし、今日の実習によって在宅医療はこの二律背反の架け橋となることがわかりました。在宅医療という手段、そして在宅医療についての正しい詳細が世に出ることで、現在悩んでいる多くの患者さんに1つでもよりよい選択肢が増えると思いました。
H29.10.11 鳥大医学部医学科4年生 大森 文子
 今回の地域医療体験学習では、訪問診療に同行させて頂き、在宅医療について見学させて頂きました。クリニックというと、患者さんが来られて診療というイメージが強く、在宅医療というもののイメージがあまりつきませんでした。しかし、一日の実習で先生方について回ることで、今まではあまり気づくことができなかった点に気づくことができ、貴重な体験をすることができました。
今回の地域医療体験学習では、訪問診療に同行させて頂き、在宅医療について見学させて頂きました。クリニックというと、患者さんが来られて診療というイメージが強く、在宅医療というもののイメージがあまりつきませんでした。しかし、一日の実習で先生方について回ることで、今まではあまり気づくことができなかった点に気づくことができ、貴重な体験をすることができました。
クリニック全体で患者の状態を把握し、日々の訪問診療に反映するためには、まず患者さんとのコミュニケーションが大切になってくると思います。先生方は患者さんとの会話の中で何か変わったことはないかを確認したり、家族の方と話をしたりすることで信頼関係を築くことにつなげているように感じました。また、電話での連絡の取り合いを頻繁に行っていらっしゃり、情報の共有がどれだけ大事なのかということを感じました。これらは病院であろうと個人のクリニックであろうと大切なことだと思うので、そのことを忘れないよう気を付けたいと思います。今回の実習では貴重な体験をさせて頂き、本当にありがとうございました。
H29.10.18 鳥大医学部医学科4年生 増田 快飛
 医学部の講義でもあまり学ぶことがなく、一般的にもまだ普及してないと思われる「在宅医療」という分野を専門にしているひだまりクリニックに今回実習をさせていただいた。実際に「在宅医療」をする前の「在宅医療」のイメージは、患者さんの家を訪問して、患者さんの様子を伺ったり、血圧を測ったり、患者さんの家族と話をして、薬を処方したりするものだと思っていた。実際に見学した内容は先に述べたものにあまり違わなかったが、唯一イメージと大きく異なっていたことがあり、それは医師と看護師などのスタッフと患者さん、そして患者さんの家族の方々との距離が思っていたより近く、診療している間、近所づきあいをしているような感覚がした。また、患者さんの家をまわる間ずっと車で移動するので、スタッフ同士も親しく、そのおかげでとてもスムーズに診察できていたことに驚いた。この医師、看護師の連携のスムーズさは大学病院などではあまり感じないと思われた。
医学部の講義でもあまり学ぶことがなく、一般的にもまだ普及してないと思われる「在宅医療」という分野を専門にしているひだまりクリニックに今回実習をさせていただいた。実際に「在宅医療」をする前の「在宅医療」のイメージは、患者さんの家を訪問して、患者さんの様子を伺ったり、血圧を測ったり、患者さんの家族と話をして、薬を処方したりするものだと思っていた。実際に見学した内容は先に述べたものにあまり違わなかったが、唯一イメージと大きく異なっていたことがあり、それは医師と看護師などのスタッフと患者さん、そして患者さんの家族の方々との距離が思っていたより近く、診療している間、近所づきあいをしているような感覚がした。また、患者さんの家をまわる間ずっと車で移動するので、スタッフ同士も親しく、そのおかげでとてもスムーズに診察できていたことに驚いた。この医師、看護師の連携のスムーズさは大学病院などではあまり感じないと思われた。
最後に、今回実習させていただいたひだまりクリニックは小さな病院で、こじんまりとしているが、スタッフの方々が皆穏やかで、こういう方々が「在宅医療」をすると、患者さんも安心できるだろうなと感じた。
H29.10.18 鳥大医学部医学科4年生 森安 真木
 今回、ひだまりクリニックの先生と看護師さんの訪問診療に同行させていただき、見学させていただいて、イメージしかなかった在宅医療がリアリティのあるものになりました。元々、祖父を祖母が介護していて、それを支えてくれている医療従事者の方々を見ていて、医師を目指し医学科に入学したのですが、大学に入ってからは専門的な学習が多く、在宅医療に触れる機会はあまりありませんでした。初めて目の前で在宅医療の現場を見て、チーム医療がされているなということを最も強く感じました。朝のミーティングで患者さんの情報を共有し、移動の車内では患者さんやご家族の医療以外についての情報も共有されていました。在宅医療においてはもちろん患者さんの意志も大切ですが、主介護者であるご家族とコミュニケーションをとりながら、どういった処置をとるか考えていくことがとても大切なのだと思いました。また、今回は自宅だけでなく施設での訪問診療も見学させていただきましたが、ご家族が側におられない場合でも、施設のスタッフの方、看護師さん、その他コメディカルの方たちと情報を共有することで、患者さんにとってどんな医療をするか決められるのだなあと思いました。在宅でも施設でも、医師だけでなく様々な職種の人たちによって成り立っているということを実感しました。
今回、ひだまりクリニックの先生と看護師さんの訪問診療に同行させていただき、見学させていただいて、イメージしかなかった在宅医療がリアリティのあるものになりました。元々、祖父を祖母が介護していて、それを支えてくれている医療従事者の方々を見ていて、医師を目指し医学科に入学したのですが、大学に入ってからは専門的な学習が多く、在宅医療に触れる機会はあまりありませんでした。初めて目の前で在宅医療の現場を見て、チーム医療がされているなということを最も強く感じました。朝のミーティングで患者さんの情報を共有し、移動の車内では患者さんやご家族の医療以外についての情報も共有されていました。在宅医療においてはもちろん患者さんの意志も大切ですが、主介護者であるご家族とコミュニケーションをとりながら、どういった処置をとるか考えていくことがとても大切なのだと思いました。また、今回は自宅だけでなく施設での訪問診療も見学させていただきましたが、ご家族が側におられない場合でも、施設のスタッフの方、看護師さん、その他コメディカルの方たちと情報を共有することで、患者さんにとってどんな医療をするか決められるのだなあと思いました。在宅でも施設でも、医師だけでなく様々な職種の人たちによって成り立っているということを実感しました。
また、在宅医療で用いられている医療機器をいくつか見せていただきましたが、酸素マスクや栄養の注入など、病院でしか出来ないと思っていたことが、コンパクトな機器を使うことで在宅でも実現されていて感動しました。
今回はたった一日の見学で、在宅医療のほんの一部しか見れていないとは思いますが、それぞれの患者さんが様々なバックグラウンドを持っており、それに合わせてその人に合った医療を目指していく在宅医療という分野はとても興味深く、今後もっと必要になっていくのではないかと思います。とても勉強になりました。ありがとうございました。
H29.10.25 鳥大医学部医学科4年生 金 里紗
 今回、ひだまりクリニックで実習させていただき、ありがとうございました。実際の訪問診療の様子を見学したのは初めてで、大変勉強になりました。訪問診療の時間は想像よりも短く、あっという間だったなぁという印象でした。聴診器で胸の音を聞き、脈拍、SpO2、体温を測定し、その他患者さんや家族が気になっていることを確認、診察するというシンプルな内容でした。しかし、これを病院の外来で受けようと思うと、患者さんや家族の負担は何倍にもなるのだろうと感じました。わずか数分間の診察のための手間が逆に健康面に悪い影響を与えかねないと思いました。訪問診療の必要性やありがたみを今回一緒について見学させてもらったことで身を以て感じました。
今回、ひだまりクリニックで実習させていただき、ありがとうございました。実際の訪問診療の様子を見学したのは初めてで、大変勉強になりました。訪問診療の時間は想像よりも短く、あっという間だったなぁという印象でした。聴診器で胸の音を聞き、脈拍、SpO2、体温を測定し、その他患者さんや家族が気になっていることを確認、診察するというシンプルな内容でした。しかし、これを病院の外来で受けようと思うと、患者さんや家族の負担は何倍にもなるのだろうと感じました。わずか数分間の診察のための手間が逆に健康面に悪い影響を与えかねないと思いました。訪問診療の必要性やありがたみを今回一緒について見学させてもらったことで身を以て感じました。
在宅医療について、福田先生の著書などから学んだことはまず、以前より「在宅医療」「在宅での看取り」に対するニーズが60%以上となると病院内だけでの医療の提供では間に合いません。人の死が病院から家庭に移っていく端境期にある現在、在宅医療について私自身もっと知識を深めていかなければならないと感じました。また、スタート前の退院前カンファレンスが連携に欠かせないということです。実際のお家に訪問させていただくと、玄関にスロープが設置されていたり、介護用ベッド・ポータブルトイレなどの介護用品が備えられていたり、家庭環境が介護のしやすいように整えられていました。これらの準備は患者さんが病院から帰ってくる前にされていなければならないが、家族だけでは何が必要なのか分からないと思います。そんな時に、「担当者」さんからの指導を受けることで家庭環境の整備ができるのだと思い、退院前カンファレンスが医療関係者と患者さん・家族を繋ぐ大切な場なのだと感じました。
ひだまりクリニックのスタッフさんは皆さん仲良く、昼食も一緒にとるなど和気あいあいとしていて、良い雰囲気の職場だと思いました。
H29.10.25 鳥大医学部医学科4年生 堀内 萌生
 この度はお忙しい中、貴重な体験をさせて頂き、誠にありがとうございました。
この度はお忙しい中、貴重な体験をさせて頂き、誠にありがとうございました。
在宅医療は通院が困難な患者さんにとって、大変重要な存在であるということを知り、高齢化が一層進行していくこれからの時代にとって必要不可欠なものだと感じました。今までは在宅医療と往診は同義だと考えていましたが、往診は在宅医療のごく一部であり、在宅医療は患者さんが入院・通院せずに、原則在宅で医療行為を行うことだということを認識することができました。24時間体制で電話1本で医師と連絡を取ることができ、必要に応じて駆けつける態勢が整えられているため、在宅のまま病院と大きく変わらず医療行為を受けられる点は患者さんとそのご家族にとって大きな利点の一つになるのではと感じました。入院となると、普段と環境も変わり患者さんご自身もご家族も不安を感じたり、様々な負担も増えますが、在宅診療では今まで日々を過ごしてきた自宅に居続けられるため、それだけでも心の安らぎが保たれやすくなると思いました。ただし、在宅医療の成立には患者さんの日常を支えるご家族の存在が必要不可欠だということもよく分かりました。家庭のあり方は実に多様であり、在宅医療に適応するか否かに関わる重要な事柄であるため、ご家族と患者さんの関係性、家庭環境、ご家族の方がどの程度医療的処置を行えるか等を慎重に考慮していく重要性を感じました。
ひだまりクリニックは、医療スタッフ間の連携を密にとられている印象を受けました。朝のカンファレンスでも、患者さんのご家族の詳しい情報も共有されていて、患者さんにかかわることはどんなに小さな事柄でもスタッフ全員で把握する大切さを感じました。そのような医療スタッフ間のコミュニケーションが在宅医療を支える柱の一つになっていることがよく分かりました。訪問診療の際も、医学生の私にも分かるよう、優しく教えて頂き、本当にありがとうございました。一人ひとりの患者さんに丁寧に優しく向き合っていらっしゃる先生方と看護師さんの姿が大変印象に残りました。ご家族のご苦労もきちんと配慮されていて、患者さんとの話し方、ご家族との話し方等も大変勉強になりました。
訪問診療を見学させて頂き、医療の現場は病院だけではなく、様々な場所(施設、自宅等)に患者さんが待っておられるということを実感することができました。在宅医療や介護、ケアについての知識を一層深めていきたいと思います。
たくさんのことを学ばせて頂き、誠にありがとうございました。
H29.11.1 鳥大医学部医学科4年生 村岡 萌子
 今回、初めて実習で在宅医療の現場を見させていただきました。地域医療実習という形でひだまりクリニックを訪ねさせていただいたのですが、訪問診療の経験は今までしたことがなく、とても新鮮で学ぶことがたくさんありました。
今回、初めて実習で在宅医療の現場を見させていただきました。地域医療実習という形でひだまりクリニックを訪ねさせていただいたのですが、訪問診療の経験は今までしたことがなく、とても新鮮で学ぶことがたくさんありました。
午前中、何軒かのお宅を訪問させていただき、様々な患者さんを診ました。認知症の方や、耳がよく聞こえない人。感謝の言葉を述べられるおだやかな方もいらっしゃいました。少しの診察も嫌がられ拒まれる方もいらっしゃいました。そんな中でも、院長先生をはじめ他の先生、看護師さんは一人ひとりに優しく同じ目線で話され、対応されており、在宅医療のあり方を見たと思います。また、在宅医療は患者家族と医療者のコミュニケーションがとても大切だと痛感しました。訪問看護・診療では普段の患者の状況は分かりません。家族が適確な報告をし、ちょっとした疑問もたずねることで、在宅でうまれる不安も除かれ、医療者ともよい関係を築くことができると共に、よい治療もできると考えます。
今回の実習で、患者・その家族と寄り添うことが在宅医療の一番の根幹ではないのかと感じました。本日は、お忙しい中、優しく説明してくださりありがとうございました。
H29.11.1 鳥大医学部医学科4年生 山本 光紘
 今回の地域医療体験実習は「ひだまりクリニック」で実習させて頂きました。
今回の地域医療体験実習は「ひだまりクリニック」で実習させて頂きました。
「ひだまりクリニック」は、在宅医療専門のクリニックです。独力で通院できない患者さんを中心として、基礎疾患の治療に加えて、嚥下機能を含めた食事、排泄・排尿、清潔や褥瘡に関わる整容に注意しながら診察を行います。
今まで在宅医療という言葉を耳にした事はありましたが、具体的にどのような医療なのか明確なイメージはありませんでした。この度、一日を通して、実際に診察の様子を見学させて頂き、様々なお話を伺う中で、在宅医療の特徴が少しずつ分かってきたように感じます。
在宅医療では、病院での診察とは異なり、患者さんが生活されている場所を実際に見ながら、患者さんやご家族の相談に乗ったり、直接様々な指導が可能です。訪問先では、笑顔でじっくりと患者さんやご家族の話に耳を傾け、診察される医療スタッフの方々の姿はとても印象的でした。また、地域の特性の一つとして、米子地区は老老介護が多い印象でありました。地域のかかりつけ医として、介護保険制度や多職種での連携を上手に調整し、介護者の経済的・身体的負担の軽減を様々に図っておられる先生方の姿勢は学び多いものでした。また、病院では、院内の設備で対応しますが、在宅医療では、介護保険などがより利用しやすいため、患者さんの状態に合わせて、福祉をより柔軟で、充実したものにできるという事でした。
患者さんとの距離が近く、生活背景を十分に把握した上で、きめ細かい医療を行える点が、在宅医療の魅力であり、患者中心の医療であるなと感じました。
今回の実習では、授業だけでは学ぶことのできない、地域の在宅医療における診療の実際や医療スタッフの方々の思いに直接触れることができ、とても有意義な実習となりました。今後、地域医療の在り方・考え方をさらに学んでいく上で、大変参考となる貴重な経験をさせて頂きました。
H29.12.20 鳥取大学医学部附属病院卒後 臨床研修センター研修医 平山 勇毅
 私は医師卒後臨床研修で保健所での研修を選択し、地域包括ケアを学ぶ一環として一日ひだまりクリニックで実習させて頂きました。保健所で介護保険制度や要介護認定について学んだ後、それらが実際どういうサービスとなって患者さんの生活を支えているのかを訪問診療同行という形で直視でき大変勉強になりました。
私は医師卒後臨床研修で保健所での研修を選択し、地域包括ケアを学ぶ一環として一日ひだまりクリニックで実習させて頂きました。保健所で介護保険制度や要介護認定について学んだ後、それらが実際どういうサービスとなって患者さんの生活を支えているのかを訪問診療同行という形で直視でき大変勉強になりました。
往診の最中に印象的だったことの一つは、先生が患者さんに出すお薬の薬価を気にされる場面があったことです。大学での学習・研修では適切な診断と治療について学び、最も効果のある治療を選択することを学び続けます。そこにコストの概念を挟んで考える機会はあまりありません。医療機関の役割の違いと言ってしまえばそれまでですが、患者さんの経済的負担を慮ることは、より患者さんの実生活に即した医療を提供することであり、どんな時でも心に留めておく必要があると感じました。
また、ひだまりクリニックには電子カルテが導入されており、往診先でもそれをノートパソコンで閲覧できるシステムが整っていることには驚きました。さらに、ポータブルプリンターも携帯されており、臨時往診先で紹介状を記入印刷し、素早く高次医療機関に紹介することもできます。掛かっているコストは少なくないであろうに技術の進歩を患者さんに還元できている様子は感動を覚えました。
往診での診察時には、状態の評価だけでなく、患者さんやご家族との歓談に多く時間を割いておられ、この点でも地域を診る医者としての役割の違いを感じました。本日往診したご家庭は鍵の掛かっている家が一つもなく、皆自然に私達スタッフを受け入れてくれました。地域に溶け込むとは、つまりこういうことなのだろうと思いました。
患者さんの人生は当然病院にいない時間の方が長く、家庭で過ごす時間にこそ、その本質があると思います。医者の第一義は病気を治すことかもしれませんが、患者さんの家庭での生活を支える医療者の在り方を間近で見て、自身の医者としての理想像の再確認ができました。
本日は大変お世話になりました。また米子で働く上でご一緒する機会も多いかと存じます。
今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。