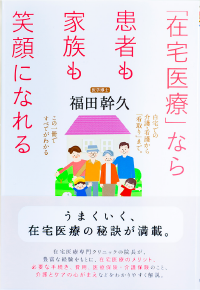2019年度実習生
R1.10.09 鳥取大学医学部医学科4年生 石原 正太郎
 今回、訪問診療に同行させていただく中で感じたのは行く先々の患者さんがとても生き生きしておられた事です。症状としては比較的重いのではないかと思われる方も、顔色もよく親しげに先生と話されているのを見ると病気を持っておられるのが信じられないくらいでした。自宅で過ごしていると、患者さんの子供や、親類などとの交流も、入院しているよりも多いように思われますし、その事によって日々のメリハリにもつながっていっているのではないかと感じました。
今回、訪問診療に同行させていただく中で感じたのは行く先々の患者さんがとても生き生きしておられた事です。症状としては比較的重いのではないかと思われる方も、顔色もよく親しげに先生と話されているのを見ると病気を持っておられるのが信じられないくらいでした。自宅で過ごしていると、患者さんの子供や、親類などとの交流も、入院しているよりも多いように思われますし、その事によって日々のメリハリにもつながっていっているのではないかと感じました。
先生のお話から在宅医療では24時間体制の医療が必要であるという事も知りました。在宅医療では、患者さんの自宅を病室のようにとらえるために、連絡をうけるといつでも医師が直接、間接問わず指示を出す必要があるためです。この体制は、医師の数が多ければ多いほど一人当たりの負担が減るので、開業医どうしの連携など行っている所も多いかもしれませんが、時間ごとの分担をするなど、よりシステマティックな形にしていくことで、医師も無理のない形で、精神的により安定した、お金もかからない在宅医療を実現できるのではないかと思います。
在宅医療という形の医療の核には、QOLの向上、あえて言うならば長生きを第一の目的とするわけではない、ということがあると感じました。医師として、病院でならできることが、ポータブルの医療器具が改善されてきているとはいえ、万全にはできない中で、患者さんや、そのご家族の希望をしっかり汲み取っていかなければならないというのはつまり、QOLの向上に長生きすることと同等かそれ以上の重要性を見ているからだと思います。今回、在宅医療の実際を見学させてもらって実感した“健康”よりも“幸せ”を意識した医療を見て、医学の新たな段階を学んだ気がします。
R1.10.09 鳥取大学医学部医学科4年生 藤岡 里奈
 今回のひだまりクリニックの研修では、午前・午後を通して訪問診療に同行させていただきました。このクリニックでは本当にたくさんの患者さんを見ておられて、先生、看護師さん共にとても忙しそうでした。患者さんはベッドで寝たきりの方が多く、また認知症の方も多かったです。世話をされる方も高齢の方が多くて、介護等をどのように行っておられるのかを実際に確認できるのが、訪問診療の良いところだと感じました。
今回のひだまりクリニックの研修では、午前・午後を通して訪問診療に同行させていただきました。このクリニックでは本当にたくさんの患者さんを見ておられて、先生、看護師さん共にとても忙しそうでした。患者さんはベッドで寝たきりの方が多く、また認知症の方も多かったです。世話をされる方も高齢の方が多くて、介護等をどのように行っておられるのかを実際に確認できるのが、訪問診療の良いところだと感じました。
高齢化が進み、また早期退院を勧められる日本において、これから医療の現場は病院だけにとどまらず、また施設や在宅で治療したい、看取られたい、と願う患者さんも増えていくのだと思います。患者さん一人ひとりの家族構成や生活背景、環境、意志や希望をより考慮した医療を実現できるのが、この在宅医療なのではないかと思いました。また、先生方やスタッフさんも決して一人で全てを行っているわけではなくて、より詳しい先生に相談したり、またデイサービスといった施設と連携してより広く医療をされている姿が印象的でした。様々な職種の人が関わってより多角的に患者さんを診ていくことで、患者さん一人ひとりに対する医療の質は向上していくと思います。
今回の実習を通して今の日本の直面する高齢化に伴う患者数の増加や病床数の不足の中で、訪問診療及び在宅医療は不可欠のものとなってくると考えられます。今回こういった機会を通して在宅医療について学ばせていただくことができ、本当によい経験になりました。
この度はお忙しいところ私たちの実習を受け入れて下さりまことにありがとうございました。
R1.10.16 鳥取大学医学部医学科4年生 古川 美紀
 今回、地域医療実習の一環としてひだまりクリニックにお邪魔させていただきました。これまで行ってきた実習で在宅医療に触れる機会は何回かありましたが、訪問診療のみを行っているクリニックは初めてでたくさんの発見がありました。
今回、地域医療実習の一環としてひだまりクリニックにお邪魔させていただきました。これまで行ってきた実習で在宅医療に触れる機会は何回かありましたが、訪問診療のみを行っているクリニックは初めてでたくさんの発見がありました。
まず印象的だったのは朝のカンファレンスで、医師と訪問看護師の方々が、前日に訪問診療を行った患者さんの情報共有を行っていました。その時に、「○○さんは~で・・・」、「あー、あの方はね・・・」というふうに、約350人の患者さんを皆さんが把握されていることに驚きました。また、カンファレンスにおいて患者さんの家族の中でのキーパーソンを決めるのが大事ということをおっしゃられていたことにもすごく納得しました。このように患者さんの病態だけでなく患者さんの家族や暮らしまでを把握するのには、丁寧な診察とコミュニケーションが大事なのだなと思い、実際に福田先生の訪問診療に同行させていただきそうした姿勢を目の当たりにすることができました。
また、今までの実習で見てきた在宅医療は、手書きのカルテを用いていたり、在宅で最低限できることしか行っていなかったのですが、ひだまりクリニックではパソコンでカルテを書いたり、時にはポータブルのCTや血液ガス分析装置などを用いていて、在宅医療でできることの幅が広がっているのだなということが分かりました。
今日の実習では在宅医療のほんの一部しか見れていないとは思いますが、何よりも患者さんのバッググラウンドを把握し患者さんそれぞれに合わせた医療を提供しようとする姿勢を学ぶことができました。今日一日大変お世話になりました。
R1.10.16 鳥取大学医学部医学科4年生 水越 太志郎
 今回の実習で、私は初めて在宅医療というものに触れました。今まで在宅医療という言葉は知っていたものの、どういったものでどのように行っているのか知りませんでした。なので、今回実習させて頂いてとても勉強になりました。訪問診療において、まず一番印象に残ったのは、患者さんとの距離が病院での外来と比べてとても近い、ということでした。もちろん、血圧を測ったり、血糖を測ったりという診察はしていましたが、患者さんと話をする時間が長くとられていたと思います。また、患者さんだけでなく、その家族との会話もよくされていました。日常会話も多かったですが、先生曰く、患者さんの家族は家でその患者さんをずっと見ているので小さな変化にも気付きやすい、とのことで納得しました。また、在宅医療を行うにあたり、最初にカンファレンスでキーパーソンを決めるのが大切、ということも興味深かったです。在宅で患者さんをみるにあたり、人間関係はとても大事で、誰を中心に話を聞いたり、治療の方法を決めるか明確にしておくのが必要なようでした。
今回の実習で、私は初めて在宅医療というものに触れました。今まで在宅医療という言葉は知っていたものの、どういったものでどのように行っているのか知りませんでした。なので、今回実習させて頂いてとても勉強になりました。訪問診療において、まず一番印象に残ったのは、患者さんとの距離が病院での外来と比べてとても近い、ということでした。もちろん、血圧を測ったり、血糖を測ったりという診察はしていましたが、患者さんと話をする時間が長くとられていたと思います。また、患者さんだけでなく、その家族との会話もよくされていました。日常会話も多かったですが、先生曰く、患者さんの家族は家でその患者さんをずっと見ているので小さな変化にも気付きやすい、とのことで納得しました。また、在宅医療を行うにあたり、最初にカンファレンスでキーパーソンを決めるのが大切、ということも興味深かったです。在宅で患者さんをみるにあたり、人間関係はとても大事で、誰を中心に話を聞いたり、治療の方法を決めるか明確にしておくのが必要なようでした。
患者さんや家族との関係が大切な訪問診療ですが、先生は訪問先での会話から、周囲の人に信頼されているのが伝わり、素晴らしい診療をされているのだなと感じました。私もそのような医師になれるように頑張りたいと思いました。
R1.10.16 鳥取大学医学部医学科4年生 西川 ゆかり
在宅医療を専門にしているクリニックであることは、学生の時から存じ上げておりました。今回は米子保健所での研修の一環としてこちらに伺うことができると知り、とても楽しみにしておりました。
朝のカンファレンスから、午前午後の診療にかけて、一日間一緒に活動させていただきましたが、利用者さまやご家族に寄り添いながら信頼関係を築かれておられる様子を拝見し、日頃、大学病院で画一的な診療に浸かりきっている自身の思考を省みるよい機会になりました。
向こう数年間は専門医取得のため、急性期病院での勤務が続きますが、主治医として患者さん・ご家族と対面する際は、それぞれの家族が各々の背景を持っていることと、自分の手元を離れて次のステップに進まれる時のことを、必ず想定しながら、臨んでいきたいと思います。
短い時間でしたが、お世話になりました。
R1.10.23 鳥取大学医学部医学科4年生 陰山 佳奈
 今回の実習でひだまりクリニックにお世話になり、在宅医療に特化した医療機関に来たのが初めてだったので、多くの発見がありました。今まで入院しなければならないと思われていたかなりの部分まで在宅で見れるようになったことで、自分の家で過ごしたいという患者さんのニーズに応え、高齢化が深刻な日本の医療を支えるのにとてもすばらしい形態だと思いました。また、訪問診療だけでなく、薬も薬局から届けてもらえたり、訪問看護や訪問リハビリといったサービスが充実していることに驚きました。訪問診療に同行させていただく中で、電話ですぐに訪問看護と連絡を取っている場面や、ノートに記録するといった連携が多々見ることができ、まさにチーム医療だなと思いました。
今回の実習でひだまりクリニックにお世話になり、在宅医療に特化した医療機関に来たのが初めてだったので、多くの発見がありました。今まで入院しなければならないと思われていたかなりの部分まで在宅で見れるようになったことで、自分の家で過ごしたいという患者さんのニーズに応え、高齢化が深刻な日本の医療を支えるのにとてもすばらしい形態だと思いました。また、訪問診療だけでなく、薬も薬局から届けてもらえたり、訪問看護や訪問リハビリといったサービスが充実していることに驚きました。訪問診療に同行させていただく中で、電話ですぐに訪問看護と連絡を取っている場面や、ノートに記録するといった連携が多々見ることができ、まさにチーム医療だなと思いました。
在宅における医療であるために、家庭環境やだれが看るのかといった点で対応していく難しさがあると感じました。老老介護や、介護力の低い場合には、患者さんだけでなく、ご家族の生活が成り立つように、サービスを増やしたり、それに合わせた医療行為を考慮していくことが重要であると学びました。
今回ひだまりクリニックに来させていただいたことにより、医療のあり方に対する考え方が変わったと思います。柔軟な思考を持って、患者さんやご家族が過ごしやすいような医療を提供できる医療人でありたいと思いました。一日、ありがとうございました。
R1.10.23 鳥取大学医学部医学科4年生 藤井 直人
 今日は地域医療体験という形で在宅医療を見させていただきました。鳥取県出身ということもあり、これから向き合っていくことになる医療であると思うので、今回このような貴重な体験ができ、とても勉強になりました。
今日は地域医療体験という形で在宅医療を見させていただきました。鳥取県出身ということもあり、これから向き合っていくことになる医療であると思うので、今回このような貴重な体験ができ、とても勉強になりました。
「在宅医療」を実際にみる前のイメージは、体調が悪いとおっしゃった患者さんの元へ行き、診察して、お薬を出して、終わりといったようなものでした。しかし、実際の「在宅医療」は、定期的に患者さんを診てまわり、患者さんの状況だけでなく、患者さんの生活や患者さんのご家族の精神的なケアなどとても幅広いように感じました。
そして、今回の実習で一番強く思ったことは、医師と看護師などのスタッフさんと患者さんや患者さんのご家族の距離が思った以上に近く、診察している間、まるで仲のいいご近所さんかのように楽しく会話していたことです。そのため、患者さんやご家族からの信頼が厚く、診察が終わった後に笑顔がこぼれながら家を後にする姿がとても印象的でした。
R1.10.30 鳥取大学医学部医学科4年生 山崎 佳大
 今回の実習で初めて、「在宅医療」を実際に見ること、また「在宅医療」を専門的に行っている施設を知ることができました。在宅医療は文字通り患者さんのホームグラウンドで医療者が活動を行うので、医療者のホームである、病院や診療所における診察とは違って患者さんやそのご家族のリラックスした感じ、気兼ねなく発言できる印象を受けました。末期癌や通院、通所リハビリが難しくなった患者など、在宅医療を必要とする患者さんのタイプはなんとなく想像はしていたのですが、実際このような方たちが必要としているんだなあ、ということと2人の医師で300名以上も受け持つ程、在宅医療の需要が高まっていることを実感しました。
今回の実習で初めて、「在宅医療」を実際に見ること、また「在宅医療」を専門的に行っている施設を知ることができました。在宅医療は文字通り患者さんのホームグラウンドで医療者が活動を行うので、医療者のホームである、病院や診療所における診察とは違って患者さんやそのご家族のリラックスした感じ、気兼ねなく発言できる印象を受けました。末期癌や通院、通所リハビリが難しくなった患者など、在宅医療を必要とする患者さんのタイプはなんとなく想像はしていたのですが、実際このような方たちが必要としているんだなあ、ということと2人の医師で300名以上も受け持つ程、在宅医療の需要が高まっていることを実感しました。
「地域医療学」という講義で地域医療、病院の医療を支えるさまざまなサービス、施設を知ってきましたが、今回の、在宅療養支援診療所においても、他施設、他職種との密な連絡が必要だと感じましたし、またそれをしっかりと行っていれば、訪問前からある程度準備して診察を行うことができるし、信頼して他職種と分業、協力できるのかなと思いました。
R1.10.30 鳥取大学医学部医学科4年生 松下 健太郎
 今回、全実習を含めて初めて訪問診療を見学させていただいた。訪問診療については座学においてもあまり深く触れることはなく、病院での診察という場が自宅に置き換わったものであるのだろうと自分の中で思い込んでいた。しかし、実際の現場に連いて行き見学させていただくと、病院での診察の延長線上にはないのではないかという思いに至った。そもそも病院では急性期にしろ慢性期にしろなにかしらの病気をかかえた人が入院しており、その治療と完治が目標となっていると思う。しかし、訪問診療においては、もちろんそこも目標の一端ではあるが、患者さんの思い描いている病気との付き合い方を可能な限り実現させることがゴールなのではないかと思った。したがって、病院では積極的に止めるであろう酒やタバコも、もちろん良くはないが患者さんの希望ならばある程度許されるし、病院ではなかなかできない家族との食事も家であれば可能となるだろう。このように在宅医療、訪問診療は病気を持つ人の病気を良くするだけではなく、その先の患者とその人を取り巻く人々を含めた生活に寄り添っていくものであると、今回の見学を通して考え方が変わった。
今回、全実習を含めて初めて訪問診療を見学させていただいた。訪問診療については座学においてもあまり深く触れることはなく、病院での診察という場が自宅に置き換わったものであるのだろうと自分の中で思い込んでいた。しかし、実際の現場に連いて行き見学させていただくと、病院での診察の延長線上にはないのではないかという思いに至った。そもそも病院では急性期にしろ慢性期にしろなにかしらの病気をかかえた人が入院しており、その治療と完治が目標となっていると思う。しかし、訪問診療においては、もちろんそこも目標の一端ではあるが、患者さんの思い描いている病気との付き合い方を可能な限り実現させることがゴールなのではないかと思った。したがって、病院では積極的に止めるであろう酒やタバコも、もちろん良くはないが患者さんの希望ならばある程度許されるし、病院ではなかなかできない家族との食事も家であれば可能となるだろう。このように在宅医療、訪問診療は病気を持つ人の病気を良くするだけではなく、その先の患者とその人を取り巻く人々を含めた生活に寄り添っていくものであると、今回の見学を通して考え方が変わった。
ただ、問題点もあると思う。つまり、人手不足である。今日のような在宅医療の場合、24時間対応できる形であったが、医師も1人の人間であるため体力的な面で厳しい場面は少なからずあるのではないかと思う。多数の医師が病気と向き合うだけで、その先を見ていない場合、この在宅医療は医師の不足で、破綻するのではないかとも思う。したがって、地域の開業医や大病院の医師とも場面に応じて連携し、医師一人ひとりの負担を上手分散できるような関係性を築くことが大切であると思う。具体的には訪問診療だけでは分からない検査や診断を他の病院と連携することであると思うが、これについては見学中多数見られたので、すでに確立されつつあるのではないかと思う。
これが広がっていけば、より広域をカバーでき、より大きな規模で在宅医療が可能になっていくのではないかと思う。